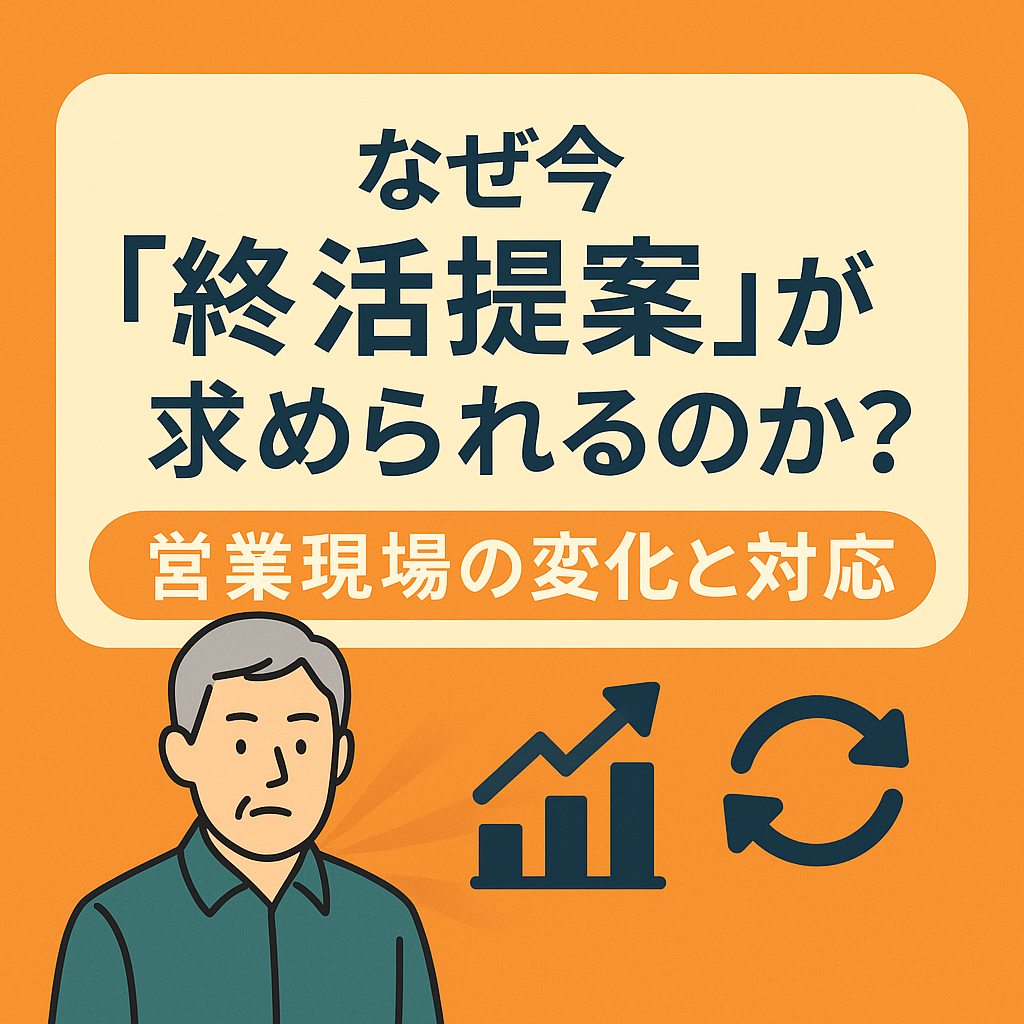
なぜ今「終活提案」が求められるのか?営業現場の変化と対応
なぜ今「終活提案」が営業現場で注目されているのか?
かつて「終活」という言葉は、ごく一部の人たちにしか関係のない話題と考えられていました。
しかし現在では、50代後半〜70代の多くが、自分の“その先”を考えることが当たり前という時代に変わりつつあります。
それに伴い、終活をテーマとした営業提案もますます注目されるようになっています。
背景にあるのは、日本社会における急速な高齢化です。
総務省の統計によると、65歳以上の高齢者人口は約3,600万人を超え、単身高齢者や子どもがいない世帯の割合も年々増加しています。
こうした変化により、老後や死後に備えることは「家族に任せること」ではなく、自分自身で意思決定すべきテーマ
さらに、終活に対する人々の意識も変化しています。
以前は「万が一に備える」「相続や介護の不安を整理する」など、リスク回避の意味合いが強かった終活ですが、
現在では「自分らしく生きる準備」「人生の後半を充実させる計画」として、前向きに取り組む人が増加
このような変化を受けて、営業の現場でも、「終活=暗い話」ではなく、ライフスタイルや価値観に寄り添う提案が求められるようになっています。
商品やサービスの紹介だけでなく、「この先、どのように生きたいか」「どんな未来を描いているか」を一緒に考えられる営業担当者が、お客様から信頼される存在になっているのです。
これまでの営業スタイルが通用しなくなってきた理由
モノ売りからコト提案へ
かつての営業は、「良い商品を紹介すれば売れる」というスタイルが通用していました。
しかし、終活市場においては、モノのスペックや価格よりも“意味”や“納得感”が重視されます。
たとえば、遺言書の作成支援や墓地の紹介といったサービスも、単なる機能説明では響きません。
「なぜ今やるべきなのか」「それがその人の人生にどう関わるのか」といった文脈を含めた“コトの提案”が必要です。
商品の先にある未来を一緒に描けるかどうかが、営業としての信頼を左右します。
高齢者の情報リテラシーが向上している
いまのシニア世代は、インターネットやスマートフォンを活用し、自ら情報を集めて比較検討する人が増えています。
「営業に言われたから」「家族がすすめたから」ではなく、納得して自分で選びたいという意識が高まっています。
そのため、営業担当者が一方的に説明するだけでは、信頼されません。
「この人はちゃんと私の考えを聞いてくれている」「一緒に考えてくれる」と感じてもらえることが、今の時代の終活提案には欠かせない要素です。
家族任せではなく“自分で決める”時代へ
以前は、老後や死後のことは「子どもがなんとかしてくれるだろう」と考える人が多くいました。
しかし、現代では少子化・核家族化が進み、家族がいない・頼れない・負担をかけたくないという理由から、自分で終活を進める人が増えています。
また、情報が豊富な時代だからこそ、「選択肢が多すぎてわからない」という不安もあります。
そんな中で営業担当者は、「一緒に整理し、決めていく伴走者」という立場が求められているのです。
終活提案に強い営業担当者の特徴とは?
「商品知識」よりも「人生理解力」
終活に関する営業では、商品やサービスの詳細な知識ももちろん大切ですが、それ以上に求められるのが「お客様の人生背景を理解しようとする姿勢」です。
たとえば同じ相続対策でも、子どもがいる人といない人、持ち家がある人と賃貸の人では、提案の方向性がまったく異なります。
単に商品を紹介するだけでなく、「その人のこれまで」と「これから」を聞き、人生観に合った提案ができる営業担当者こそが、終活の場面で信頼を集めています。
提案内容よりも“聴き方”が大事
終活営業では、「何を提案するか」よりも、「どう聴くか」の方が重要な場面が多々あります。
お客様が本当に不安に思っていることは、最初から言葉になって出てくるわけではありません。
それを引き出すには、共感を軸にしたヒアリングスキルが欠かせません。
押し売りではなく、「この人になら話せる」と思ってもらえる空気感をつくれる人が、終活分野で活躍しています。
質問よりも“相手の沈黙を待つ力”が、時に大きな成果につながるのです。
不安ではなく希望に寄り添う姿勢
「終活=不安や死に備えること」というイメージはまだ根強くありますが、営業担当者としては、そこを“前向きな人生の選択”として提案できるかがポイントです。
不安をあおって契約を取るのではなく、「こうしておけば、家族が安心ですね」「これからの時間をもっと大切にできますね」と、お客様が未来に希望を持てる言葉かけを心がけましょう。
終活は“支える営業”が選ばれる時代です。
終活営業に求められる対応力・スキルとは?
ヒアリング力:相手の価値観を引き出す
終活営業で成果を出すには、相手が言葉にしていない本音や価値観を引き出す力が欠かせません。
「何が必要か」ではなく、「どう生きたいか」「何を大切にしているか」を探るヒアリングができる営業担当者ほど、お客様との距離を縮めやすくなります。
そのためには、単なる質問の羅列ではなく、共感と沈黙を恐れない会話力が求められます。
「この人は私の話をちゃんと聞いてくれている」と感じてもらえる時間を積み重ねてこそ、本音のニーズが現れてきます。
提案設計力:複数サービスの組み合わせ
終活に関するニーズは多岐にわたります。
エンディングノート、保険、相続、住まい、介護、葬儀…と、一つの商品で完結するケースは少なく、複数サービスの組み合わせで初めて「納得の終活」が実現することがほとんどです。
そのため、営業担当者には「何を提案するか」だけでなく、どう組み合わせるか・何から優先するかといった“設計力”が求められます。
すべてを一度に勧めるのではなく、お客様の今の状況や意欲に応じた段階的な提案が重要です。
信頼構築力:時間をかけて寄り添う姿勢
終活営業において、スピード勝負は通用しません。
むしろ、「急がせる営業」に対して高齢者は警戒心を持つため、時間をかけて信頼を積み上げる姿勢が必須です。
「今日決めてもらう」ではなく、「いつでも相談できる相手でいる」ことを大切にする方が、長期的には大きな成果につながります。
その中で紹介や口コミも広がりやすく、“人”として信頼される営業担当者になっていくのです。
まとめ|これからの営業は“終活提案力”が鍵になる
高齢化が進む日本社会において、終活はもはや一部の人のためのものではなく、誰もが向き合うべき人生のテーマとなっています。
その中で営業担当者に求められる役割も大きく変わりつつあります。
商品を「売る」だけではなく、お客様と「これからを考える」。
一人ひとりの人生に寄り添い、「どう生きたいか」「どうありたいか」を引き出し、その人らしい未来を一緒に設計すること。
それが、現代の終活営業に求められる姿です。
もちろん、提案のテクニックやサービス知識も重要です。
しかし、何よりも大切なのは、お客様に「この人に相談してよかった」と感じてもらえる信頼関係を築くこと。
終活という繊細なテーマだからこそ、そこには丁寧な対応力と深い理解力が問われます。
これからの時代、終活提案ができる営業は、“価値ある相談相手”として選ばれる存在になります。
人生の節目に寄り添える営業力は、業種を超えて今後さらに重宝されていくはずです。
お客様の未来をともに考える「終活提案力」。
ぜひ、あなたの営業スタイルに取り入れてみてください。
終活提案に関するご相談、お気軽にどうぞ
「終活の提案に自信がない…」「お客様との会話がなかなか続かない…」
そんな悩みをお持ちの営業担当者の方へ、シニアテラスでは終活提案に役立つノウハウや支援サービスをご案内しています。
営業現場での困りごとや、具体的な提案方法についてのご相談も大歓迎です。
まずはお気軽に、下記よりお問い合わせください。

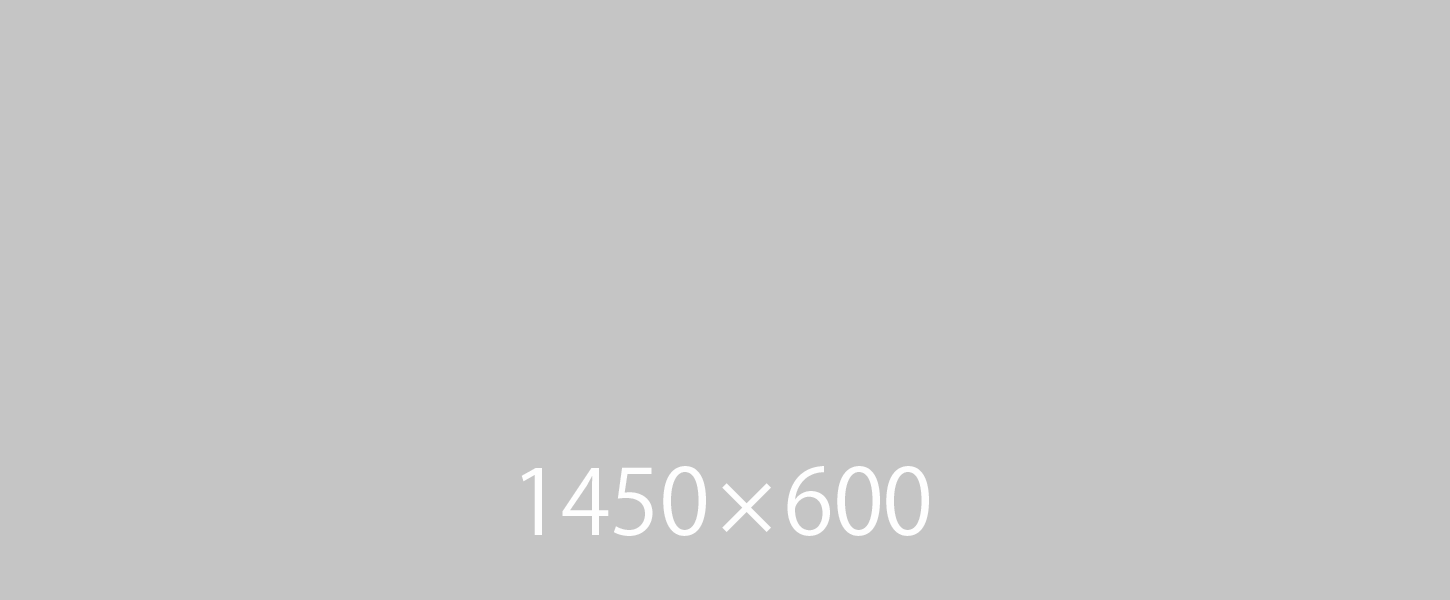
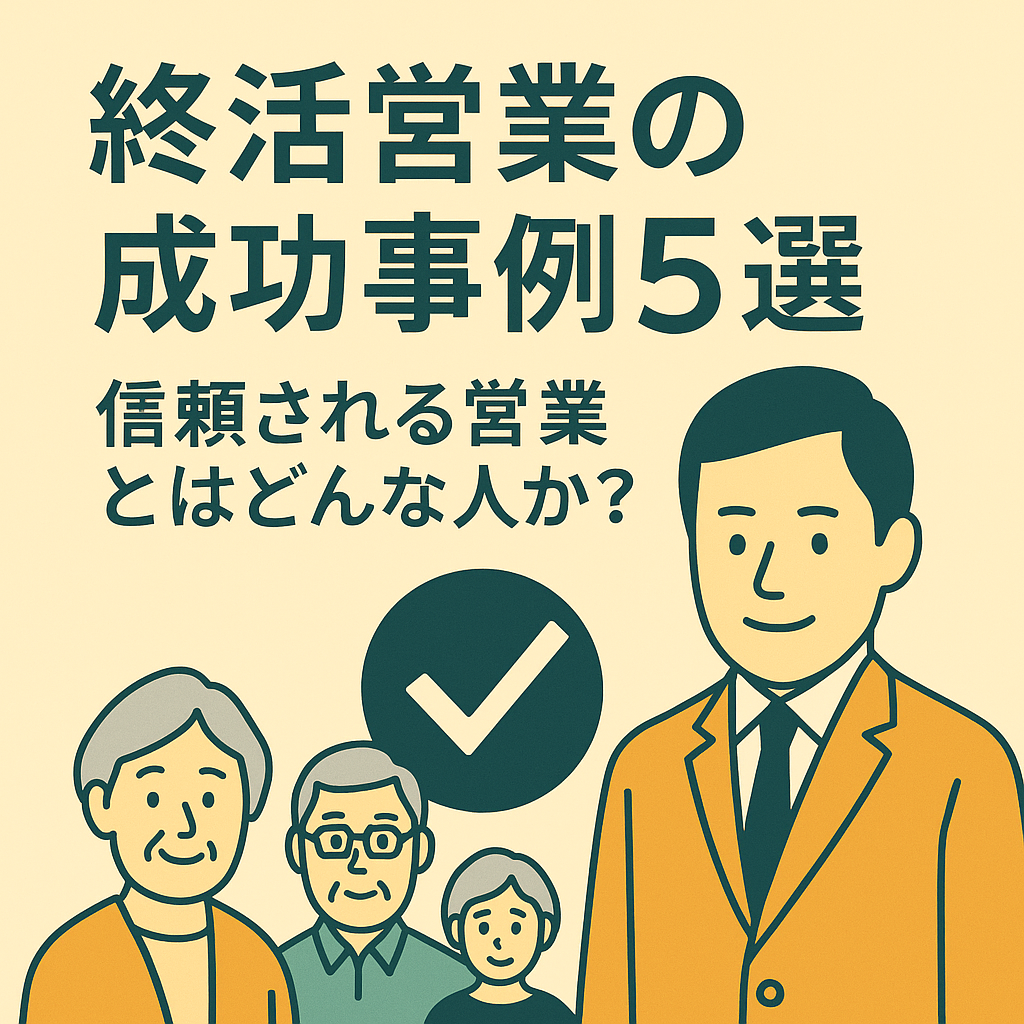

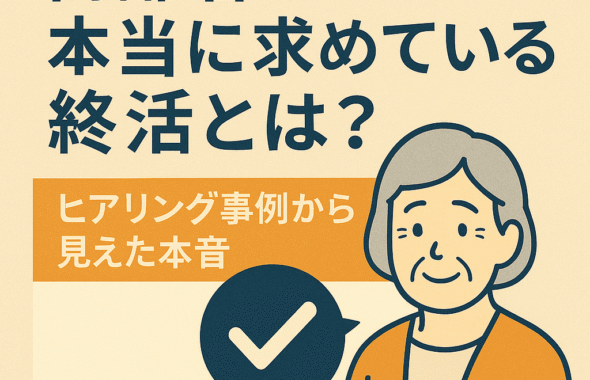
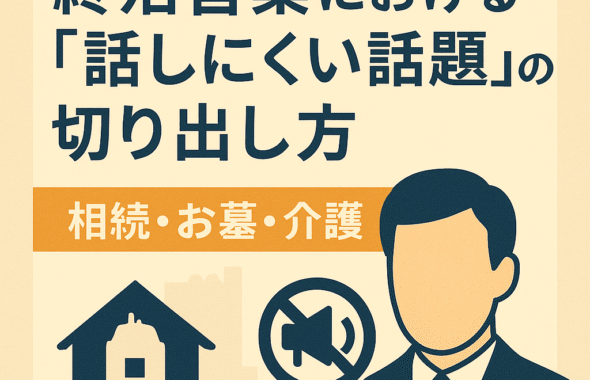

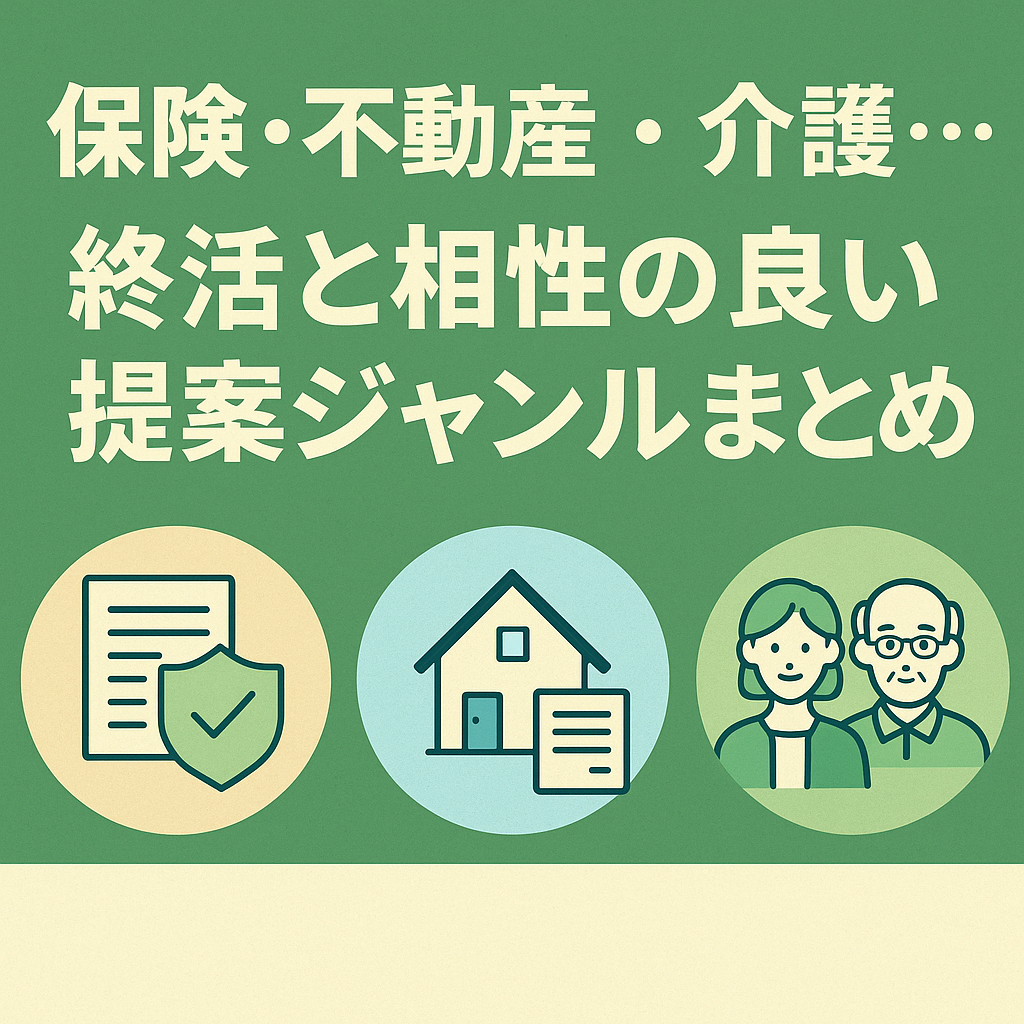
この記事へのコメントはありません。