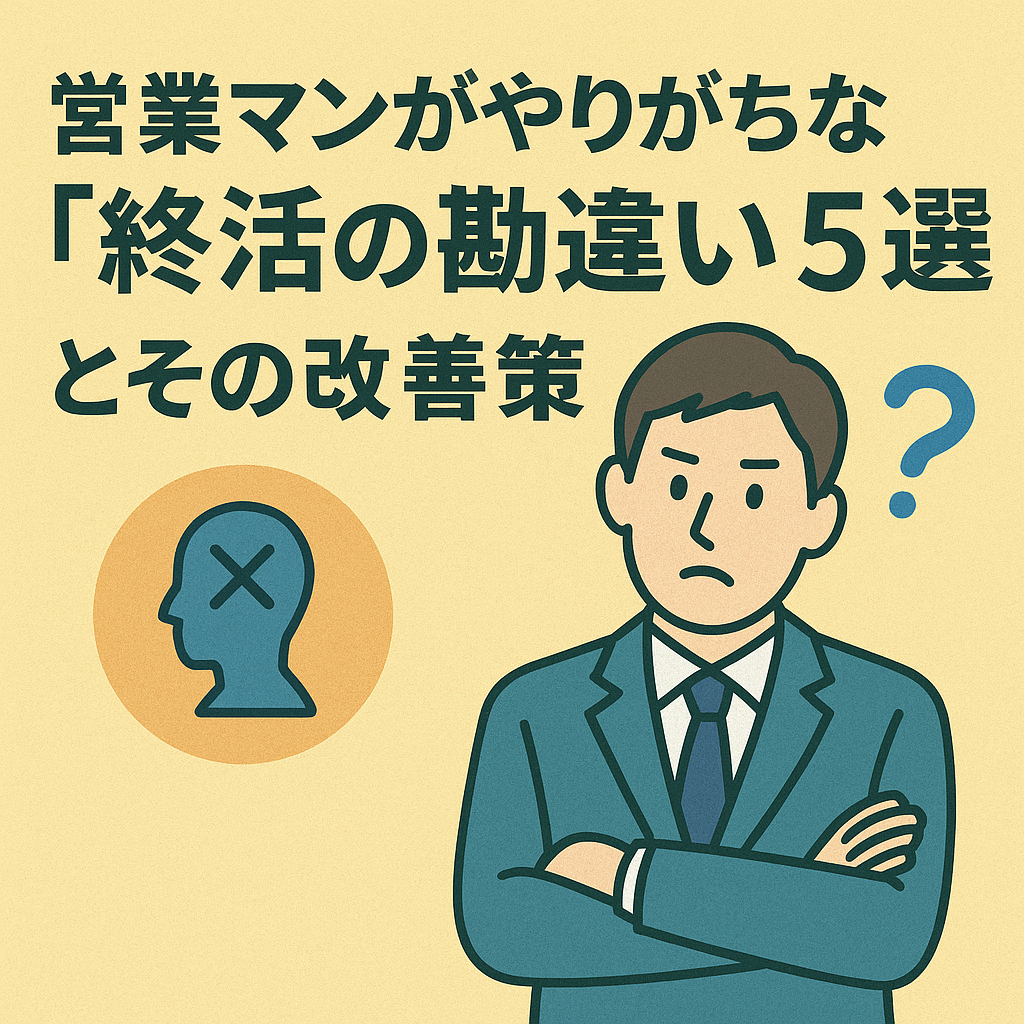
営業マンがやりがちな「終活の勘違い」5選とその改善策
なぜ終活営業で「勘違い」が起きやすいのか?
終活営業に取り組む営業担当者の中には、「うまく提案できない」「会話が噛み合わない」といった壁にぶつかる方が少なくありません。
実はそれ、多くの場合は知識やスキルの不足ではなく、“思い込み”や“勘違い”によるミスマッチが原因になっています。
終活は、お金・モノ・制度の話だけでなく、人生観・価値観・感情が深く関わるテーマです。
そのため、従来の営業スタイルで通用するとは限りません。
「ニーズを見つけたらすぐクロージング」
「商品説明は分かりやすく早く伝える」
といった手法が、むしろ“不信感”や“押し売り感”につながってしまうこともあります。
また、終活に対して営業側が“高齢者のための話”や“死に備える暗いテーマ”と決めつけてしまうと、本来の希望や前向きな動機を見落としてしまうことにもなりかねません。
つまり、終活営業で成果を出すためには、まず自分自身の「終活に対する捉え方」をアップデートすることが重要なのです。
次章では、実際の現場でよくある勘違いとその改善策を5つご紹介します。
営業現場でよくある終活の勘違い5選と改善策
ここでは、実際に営業現場でよく見られる「終活の勘違い」を5つ取り上げ、それぞれの改善策とセットで解説します。
ちょっとした意識の違いが、大きな信頼の差になります。
① 終活=お墓や遺言の話だけだと思っている
終活というと、「相続」「遺言」「お墓」といった限定的なイメージを持つ営業担当者が多くいます。
しかし実際は、住まい・保険・介護・趣味・デジタル整理など、人生全体を整える活動であり、提案できる領域は非常に広いのです。
改善策:終活の全体像を把握し、自社商材との接点を探ることから始めましょう。
「これも終活の一環ですよ」と伝えられるだけで、お客様の関心が変わります。
② 終活は「高齢者にだけ」必要なものと決めつけている
「終活は70代以降の人がやるもの」という思い込みも、多くの営業で見られる勘違いです。
実際には、50代・60代の“親の終活サポート世代”や、自分の人生を見直したい層が動き始めています。
改善策:年齢で区切るのではなく、ライフステージや関心で終活ニーズを捉える視点を持ちましょう。
「まだ若いから」ではなく、「今だからこそ考えておきたいこともある」という提案が、響くきっかけになります。
③ 不安や弱さを刺激して“急がせる”トークを使っている
「このまま何も準備しなければ、大変なことになりますよ」
「亡くなった後に家族が困ることになります」
といった“不安をあおるトーク”は、かえって相手の警戒心を強める原因になります。
終活は慎重に進めたいテーマ。
だからこそ、「急がされる=売り込み感」と捉えられてしまうと信頼を失いかねません。
改善策:「これをやっておくと安心ですね」「前もって考えておくと、気持ちが楽になりますよ」など、前向きな安心感を軸にした提案に切り替えましょう。
“せかさず寄り添う”姿勢こそが、終活営業において最も効果的なアプローチです。
④ 自社商品のメリットばかりを説明してしまう
終活提案でありがちなのが、「自社の商品がどれだけ便利か」「どれだけコスパが良いか」を一方的に伝えてしまうことです。
しかし、高齢者にとって重要なのは、“その商品が自分の人生にどう関わるか”という実感です。
「説明は分かりやすかったけど、なんとなく売られた感じがした」
そんな印象を持たれてしまっては、せっかくの提案も響きません。
改善策:商品の話をする前に、お客様の人生観や想いをしっかり聴くことを優先しましょう。
「それなら、こういった方法もありますよ」と提案する流れにすれば、商品が“解決策”として自然に受け入れられます。
⑤ 本人ではなく家族にばかり話してしまう
終活の提案では、ご家族(特に子ども世代)が同席していることも多くなります。
その際によくあるのが、つい家族の方ばかりに話してしまい、ご本人の存在が置き去りになるパターンです。
本人が「自分のことなのに、勝手に話が進んでいる」と感じてしまうと、信頼は一気に失われます。
改善策:必ず本人を中心に置き、「〇〇さんは、どうお考えですか?」と問いかけることを忘れないようにしましょう。
家族の意見も大切にしつつ、あくまで意思決定者は“ご本人”であるという姿勢が、終活提案では最も重要なマナーです。
終活営業における信頼構築の基本とは?
終活営業で成果を出している営業担当者に共通するのは、「商品知識」よりも「信頼される人柄」です。
人生の終盤に関わるセンシティブなテーマを扱うからこそ、営業のスタンスそのものが提案の成否を分けます。
「何を売るか」ではなく「誰として接するか」
終活は、モノを買うというより「誰と話すか」「誰と考えるか」が重視される分野です。
お客様が営業担当者に求めるのは、便利な知識より“安心できる空気感”だったりします。
「この人は売り込みじゃない」「ちゃんと話を聞いてくれる」
そう思ってもらえるだけで、提案のハードルはぐっと下がります。
ヒアリング・共感・待つ力が営業の信頼を育てる
終活営業では、急がず、遮らず、決めつけないことが基本です。
まずはじっくりと話を聞き、「うんうん、それ大事ですよね」と共感を示す。
相手が話し出すまで“沈黙を待つ余裕”を持つ。
この積み重ねが、営業とお客様の間に静かな信頼関係を育てていきます。
自分が“相談される人”になれているかを見直す
終活営業での理想的な関係性は、「売る人」ではなく「相談できる人」です。
「〇〇さんなら話してみようかな」
「ちょっと確認したいことがあるけど、聞いてもいいかな?」
こうした“頼られる場面”が増えてきたら、それは信頼営業が機能している証拠です。
そのためには、話し方や商品説明よりも、日頃の関わり方や姿勢を大切にしましょう。
まとめ|勘違いに気づけば、終活営業は大きな信頼資産になる
終活営業で成果が出ない原因は、知識や経験不足ではなく、“ちょっとした思い込み”や“無意識のズレ”であることがほとんどです。
逆に言えば、その勘違いに気づいて修正できれば、終活は営業にとって強力な信頼構築のチャンスになります。
お客様が求めているのは、完璧な答えや商品ではなく、一緒に考えてくれる人、丁寧に話を聴いてくれる人です。
その姿勢が伝われば、提案そのものが“安心材料”となり、売り込まずとも選ばれるようになります。
終活営業は、単なるサービス提供ではなく、人生に関わる深い提案。
だからこそ、誤解を正し、思い込みを手放し、“支える営業”として向き合うことが、これからの信頼と成果につながります。
ぜひ、目の前のお客様の人生にそっと寄り添う営業を、一歩ずつ積み重ねてみてください。
終活営業で“信頼される人”を目指したい方へ
「終活営業って、どう向き合えばいいのか不安…」
「お客様との会話が、どうも噛み合わない…」
そんなお悩みがある方は、ぜひ一度シニアテラスにご相談ください。
私たちは、現場のリアルな課題に寄り添いながら、終活提案に役立つ営業トーク例・ヒアリング支援ツール・ロールプレイ研修などをご提供しています。
“売る”から“信頼される”営業へ――その一歩を一緒に踏み出しましょう。

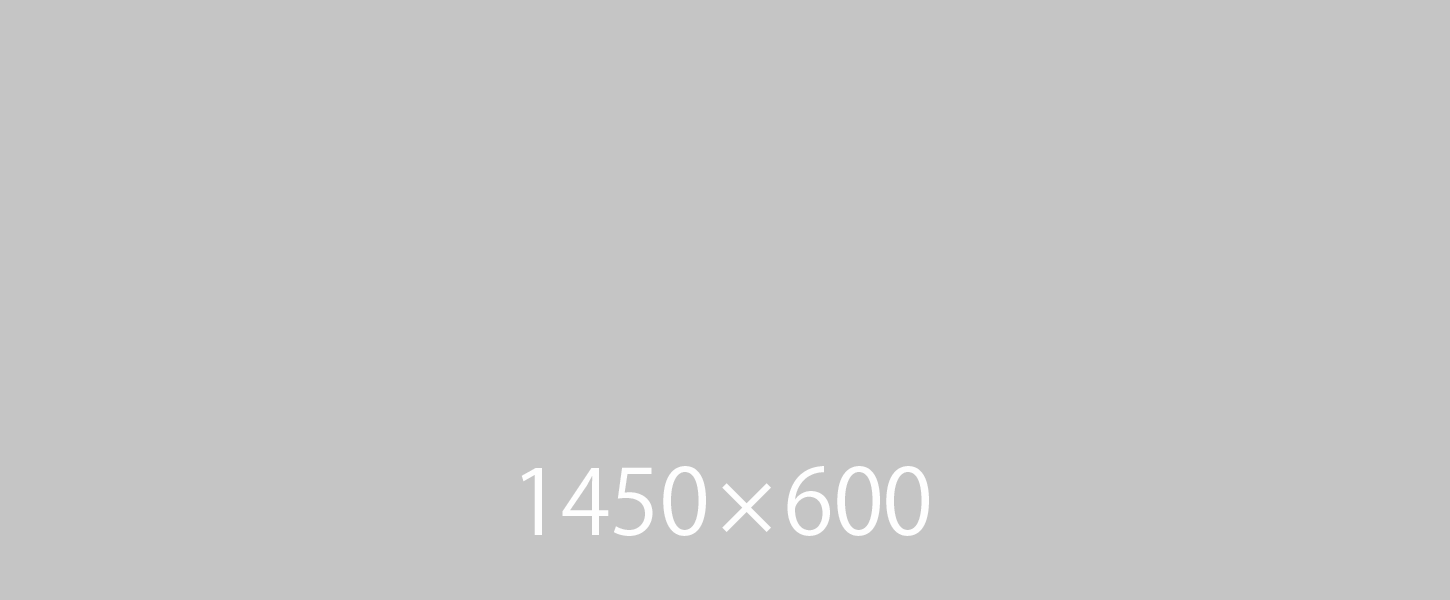
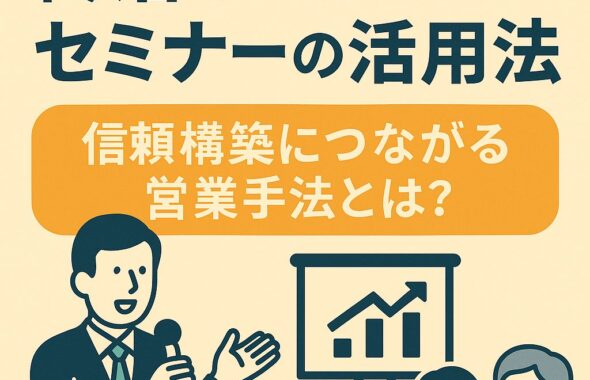

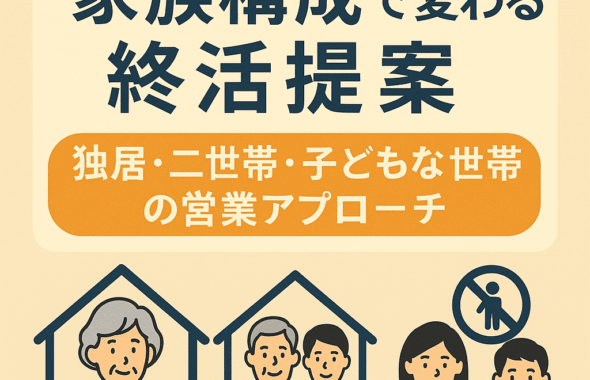
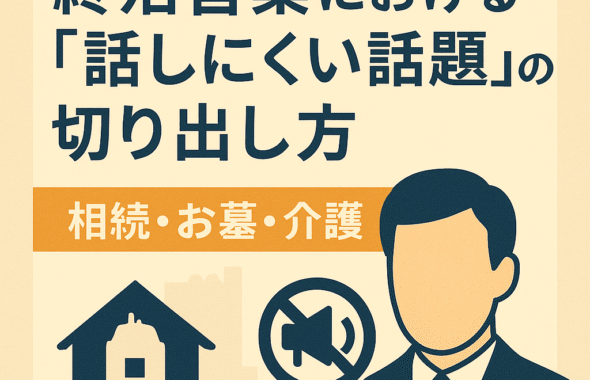

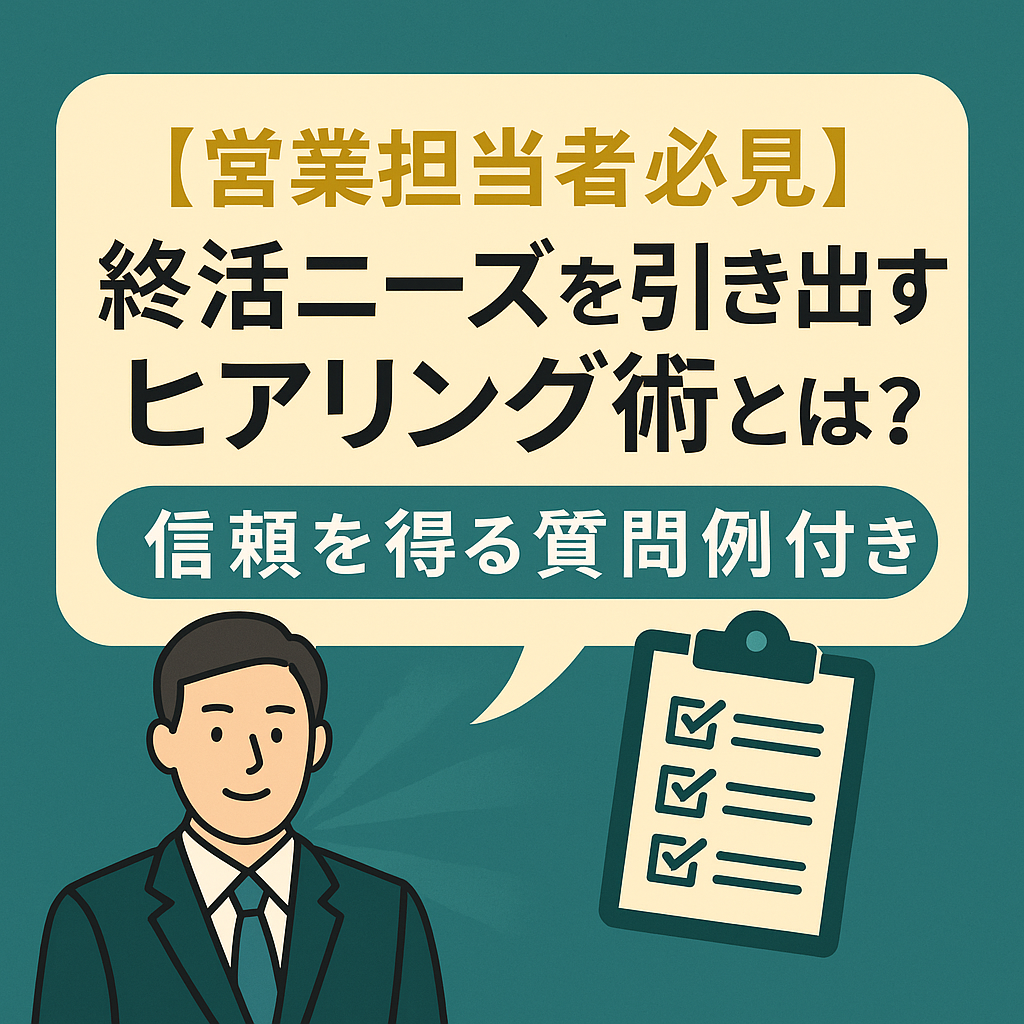
この記事へのコメントはありません。